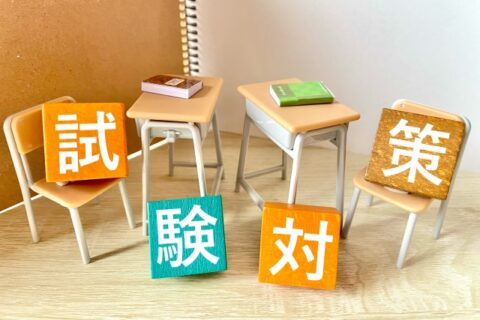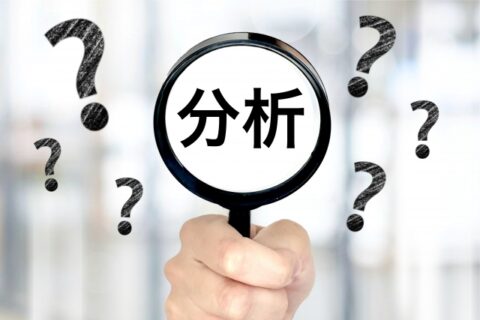例年通り、日本アクチュアリー会から今年度の同会資格試験にかかる『資格試験要領』が同会ホームページで公開されました。
そこで、今回のコラムでは、同要領を初めて御覧になる方や受験経験の浅い方を中心に、見るべきポイントなどをご紹介いたしましょう。
なお、筆者は試験委員の経験がなく、推測に基づく部分が含まれることをご容赦ください。
1.資格試験要領の掲載箇所
日本アクチュアリー会ホームページのトップ画面から下にスクロールすると「ニュース」があり、左から3番目の「試験情報」をクリックすれば、アクチュアリー試験に関するニュースが閲覧できます。
なお、“2025.07.01試験情報2025年度資格試験情報を掲載しました”と表示されるとおり、『資格試験要領』という単語がトップ画面に必ずしも登場するとは限らない点にご注意ください。
また、同会の「資格試験情報」をクリックしても『資格試験要領』にたどり着けますので、当該URLも「お気に入り」に登録しておくのもおススメです。
2.教科書の変更
試験本番に向けて、まず、教科書の変更有無をチェックする必要があります。
幸い、日本アクチュアリー会ホームページの「資格試験情報」をクリックして、下にスクロールすると、「試験科目・内容および教科書・参考書の昨年度からの変更点」が登場しますので、必ず目を通しましょう。
ざっと見る限り、教科書の大幅な変更はないように見受けられますが、改訂日の更新(例.保険1:2021年3月改訂版⇒2024年2月改訂版など)がありますので、最新の教科書で学習されるとよいでしょう。
3.出題範囲の変更
たとえ教科書の変更等がなくても、出題範囲が変更されることもあります。
例えば、生保数理(注.当時は生命保険数学1、2)のように、『教科書(下巻)第15章団体定期保険』が出題範囲に追加される場合もあります。(←今回は追加されませんでした)
この場合、平成10年度(保険数学2)問題5をチェックしつつ、「出題範囲とチェックすべき過去問」とがイメージできるくらい過去問をやりこむ意気込みで臨めば合格レベルと言えるでしょう。
なお、生保数理の『教科書(下巻)第16章団体年金保険』については、現在では、生保数理とは別科目で「年金数理」がありますので、生保数理の出題範囲となることはないでしょう。
また、『保険会社向けの総合的な監督指針』については、生保2で“Ⅲ-2-17-6(変額年金保険等の最低保証リスクについて)を削除(2026年3月末に項目ごと削除予定)”とありますので、学習範囲が削減されることを受験生のご負担も軽くなるかもしれません。
4.教科書の無償配布
まず、『教科書の改訂』および『教科書の無償提供』でURLが異なる点に注意しましょう。
特に、『教科書の改訂』のリンクが分かりにくいという受験生の声を耳にしますので、上述のURLをメモしておかれるとよいでしょう。
なお、電子データの開示で、教科書の文章などをテキストファイル形式で『コピペ』できるメリットがありますが、コピペできないものが含まれている可能性がありますので、その際は、スマホなどの文字認識アプリを利用されるとよいでしょう。
5.本人確認書類
今回から『健康保険証』が本人確認書類として認められなくなりました。理由は、“現行の健康保険証が2025年12月2日以降使用できなくなるため”です。
ただし、社員証+(健康保険)資格確認書の組み合わせは引き続き認められるようです。
6.スケジュール
「資格試験情報」をクリックすると最初に『試験日程』が目に入りますので、受験科目の日程を必ず押さえましょう。
なお、第2次試験(専門科目)は1~2日目の午前10時~13時が定着しつつありますが、第1次試験(基礎科目)については、最近、同一日の午前・午後で2科目実施するスケジュールが定着しつつあります。
いずれにせよ、受験科目の時間帯に向けて、規則正しい生活を継続することも、合格への近道と言えそうですね。
7.受験会場
受験票に、氏名および受験科目が正しく印字されているかはもちろんのこと、受験会場が正しく印刷されているかも必ずチェックしましょう。
実は、90年代の終わりに、筆者の同期が大阪勤務だった頃、誤って受験会場を東京にしてしまい、偶然、その受験生の実家が関東だったのため、会社のとりまとめ担当者もてっきり“冬休みを実家で過ごして受験するのだろう”と思い込んでしまい、さらに、受験票が到着した段階でも受験会場の誤りに気づかず、そのまま当日、大阪会場に行って初めて、自分の受験番号がないことに気付いたそうです。
幸い、2日目は東京で受験できたのですが、結果的に1日目の科目が無駄になり、来年受験し直しましたそうです。時間ロスはお金ロス以上に勿体ないことですね。
なお、CBT移行後は、東京・大阪以外でも受験可能となりましたが、第1次試験(基礎科目)と第2次試験(専門科目)で受験可能な会場が異なります。このため、特に、今年初めて第2次試験を受験される方は、申込時に必ず受験可能な会場であることを確認するようにされるとよいでしょう。
8.情報の保存
数年前までは、資格試験要領を含む情報はPDFファイルで提供されていましたが、現在は、同会ホームページの資格試験情報サイトでWeb閲覧のみとなりました。
一方、来年度以降の受験を考えた場合、昨年度からの変更点が同サイトで公開されるものの、ご自身で新旧対比表を作成し、変更点をより明確に把握された方が受験勉強がより正しい方向に進むようにも思います。
このため、例えば、Excelファイルなどに画像貼付する形で同サイトの画像を保存しておくことをおススメします。
いかがでしたか。資格試験要領も例年通りに公開され、いよいよ今年度のアクチュアリー試験が本格的に始動した感があります。一人でも多くの受験生の方が合格できるよう心より祈念いたしております。
特に、来年3月からはESR(経済価値ベースのソルベンシー規制)が導入されますので、生保2および損保2を受験される場合には、できるだけ今年の試験で合格された方が良いようにも思います。
(ペンネーム:活用算方)