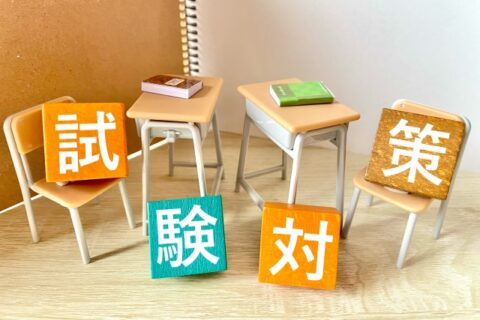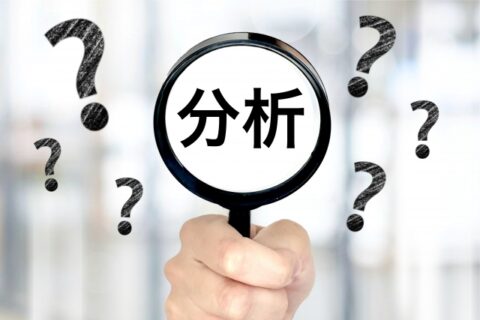先日、アクチュアリー試験(正しくは、公益社団法人日本アクチュアリー会の行う資格試験)の一科目である「生保数理」について、受験生から極めて“素朴な疑問”をいただけました。
おかげさまで、筆者はこれまで20年以上にわたって、社内外の同試験講師を務めて参りましたが、当たり前だと思っていたことを改めてストレートに聞かれたことで、改めて「生保数理」という科目の“奥の深さ”を痛感いたしました。
そこで今回のコラムでは、同試験の受験生に資するために、「連合生命の計算基数」、特に、死亡者数の取り扱いについて、思うところを順不同にてご紹介いたします。
なお、生保数理に関心のある方は、『生保数理記号の覚え方(2015年08月11日(火))』も併せてお読みいただけますと幸いです。
1.連合生命とは
被保険者が複数(=2名以上)いる生命保険を、通常、『連生保険』と呼びます。
『連生』とは『連合生命』の略称であり、例えば、『簿記=帳簿記入』などと同様に、専門用語を簡素化した表現です。
なお、生保数理の教科書を読まれた方はご存じだと思いますが、『連合生命』に対して『単生命』または『単一生命』と呼ばれる被保険者が1名の生命保険を『単生保険』と呼ばれることもあります。
2.連合生命における3つのモデル
生保数理の教科書を読まれた方はご存じだと思いますが、「連生保険」、「最終生存者連生保険」および「条件付連生保険」の3つのモデルが教科書に登場します。
これらのうち、特に、「連生保険」、「最終生存者連生保険」については、「先死亡保険」、「後死亡保険」と呼ばれることもありますが、複数の被保険者集団において、「先死亡=最初の死亡が起きたときに保険金を支払う」、「後死亡=最後の死亡が起きたときに保険金を支払う」と考えれば、それらの呼称にも一定の合理性があることがお分かりいただけることと思います。
3.連合生命の生存者数
単生命と同様、連合生命の生存者数は、{l_x+t,y+t}と表されますが、教科書(下巻)82ページの上から4行目に記載の通り、{l_x+t,y+t}={l_x+t l’_y+t}と表されます。
ここで、{l_x+t l’_y+t}をどう解釈するかがポイントですが、まず、l_xに対して l’_yという記号で、{x}と{y}とは、必ずしも同じ生命表(=死亡率)に従わなくてもよい、つまり、{x}と{y}とは独立な存在であることを示しているものと解釈されます。
つぎに、{l_x+t l’_y+t}の『量』という点に着目すれば、数学の一般論として“掛け算ではその記号『×』が省略されることがある”点を思い出せば、
『l_x+t l’_y+t = l_x+t × l’_y+t』
という関係式になると考えることが素直な考え方のように解釈されます。
しかし、後述のとおり、この“生存者数が掛け算で表される”ことで、無用な混乱が生じ得る可能性があります。
https://www.actuaries.jp/examin/textbook/pdf/seiho-suuri_2.pdf
4.連合生命の死亡者数
いよいよこのコラムの本題に入ります。
上述の通り、連合生命における生存者数は、
『l_x+t l’_y+t = l_x+t × l’_y+t』
と表されます。
それでは、連合生命における『死亡』者数は、どのように表されるのでしょうか?
教科書(下巻)109ページ上から2行目によれば、連生保険における計算基数として、
『C_xy = v^{(x+y)/2+1} × d_xy』
と表されますが、もちろん、これは単生命保険における計算基数としての、
『C_x = v^(x+1) × d_x』
という表示に対応するものです。(ただし、a^bは、“aのb乗”の意味)
問題は、『d_xy』をどのように定義するのか?という点です。
しかし、教科書を見る限り当該定義はなく、また、過去問でも当該定義を答えさせるような出題はないため、『d_xy』をどう定義するのかは不明な感じがします。
もっとも、素朴に定義しようとすれば、例えば、『d_xy = d_x × d_y』という風に考えることもできなくもないですが、実は、この定義では、連生モデルにとって不合理となる点が悩ましいところです。
5.連生保険モデルにおける『死亡』とは
連生保険モデルにおける『死亡』とは、いわゆる「先死亡」なので、複数の被保険者のうち“最初の死亡が生じたことをもってモデルにおける『死亡』とみなす”というルールになります。
したがって、もし、当該モデルにおける死亡を、
『d_xy = d_x × d_y』
と定義してしまった場合、(単生命表における)死亡者数の掛け算となってしまい、“最初の死亡”ではなく、“複数の死亡”を当該モデルの死亡とみなすことになってしまいます。
特に、初学者におかれては、このような、“教科書のゴシック体ではない部分に着目しながら、行間を読むという姿勢”が早期合格の秘訣と言えるでしょう。
いかがでしたか。7月1日に、日本アクチュアリー会試験の資格試験要領も例年通り公開されました。これから夏期休暇などを活用しながら、12月に開催される同試験の学習スケジュールを立てようとされている受験生も少なくないかもしれません。今回のコラムが特に「生保数理」の受験生にとって一助となれば幸いです。
(ペンネーム:活用算方)
2025年07月23日 (水)
連合生命の計算基数