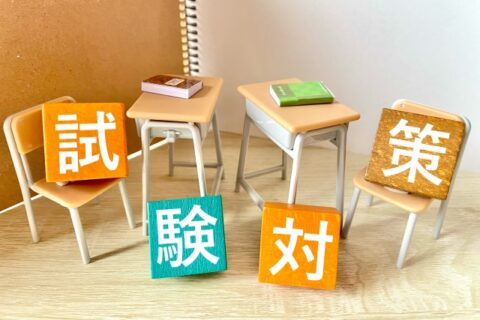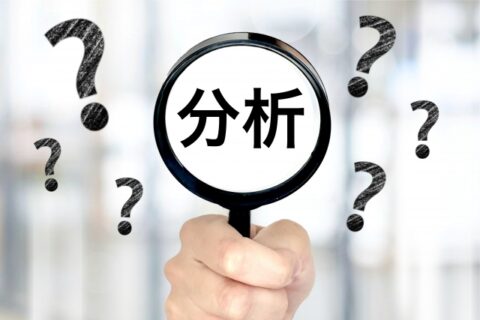先日、某コンサル会社のアクチュアリーと雑談をした際、“90年代を代表する生命保険商品の『定期付終身保険』が激減だよね”と聞かされました。
同商品は、筆者が社会人デビュー当時の『超』主力商品でしたが、念のため、生命保険協会の統計資料を調べたところ、知人の言う通り、予想以上の激減を認識しました。
そこで今回のコラムでは、『定期付終身保険』について、アクチュアリーの観点から筆者自身の備忘録を兼ねて、幾つかの想い出をご紹介いたしましょう。
1.倍率制限
筆者が社会人デビューした1994年当時、『25倍型』が“最高倍率”でした。
これは、保険金額ベースでみた“「定期保険特約+終身保険」÷「終身保険」”を『倍率』と呼称し、あまりにも高倍率な同保険は販売できないという(暗黙の)ルールでした。
その後、定期保険特約の一種である「年金払定期保険特約(生活保障特約、収入保障保険特約など)」が当該倍率制限から除外されるなど、一定の変化があったように記憶しています。
2.予定新契約費
いわゆる“更新型問題”として、当時の新聞・雑誌などでタタカレタ苦い経験がありますが、更新時に営業保険料が2倍程度に“爆上がり”することで苦情が殺到したように記憶しています。
もちろん、保険会社側としても、更新案内時に自動更新後の営業保険料水準を通知していましたが、大抵、更新後の通帳記入で当該保険料の“爆上がり”に気付いて解約という契約者行動が非常に多かった印象です。
なお、アクチュアリー的には、被保険者の年齢上昇に加えて、予定新契約費(α)の二重取り(三重取り)という「付加保険料(α-β-γ体系)」設定による問題もあり、とにかく、“保険料は一生上がりません”という名キャッチフレーズがテレビCMなどで頻発する事態に(上手く?)つながったように思います。
3.更新型と全期型
定期付終身保険の「定期保険特約」には、更新型と全期型の2つの型があり、更新型の場合には、10年や15年といった保険期間が経過すれば、自動的に更新(ただし、更新後の営業保険料は“爆上がり”)されることが主流でした。
一方、全期型の場合には、更新時の営業保険料上昇はないものの、加入当初のみを比較した場合、更新型よりも高い営業保険料となり、保険募集人からすると“全期型は売りにくい商品”という印象があったようにも思います。
4.リスク濃縮
恐らく、当該商品の“著しい特徴”といっても過言ではないのが、この『リスク濃縮』と考えられます。
上述の通り、更新時の営業保険料の“爆上がり”で多くの契約者は非更新を選択されますが、この“爆上がり”でも“更新せざるを得ない”契約が更新後の保険群団に滞留することによって、更新後の経験死亡率が悪くなり、危険差損の温床になってしまいます。
なお、(法人向けの)逓増定期保険でも同様の事象が発生することが多く、具体的には、解約返戻金(解約払戻金)のピークが過ぎても解約しない選択をした契約の経験死亡率も悪くなり、危険差損の温床になる可能性が高くなります。
5.定期保険との保険料逆転
定期保険(単品商品)と定期保険特約を比較した場合、当該特約の方が営業保険料が安いため、“高倍率の”定期付終身保険の営業保険料が、同じ保険金額である定期保険よりも安くなる現象が(理論上)起こりえます。
実際の販売条件では、当該現象が生じないような範囲で販売されることが通例なのですが、算出方法書などの基礎書類を作成する場合には、絶対に見逃してはならない要素の1つとなります。
6.特約の保険期間
通常、主契約(終身保険)の保険料払込期間と特約の同期間は一致することが多いのですが、いわゆる“終身医療保険特約”を付加する場合は、若干事情が異なるケースもあります。
具体的には、主契約の保険料払込期間満了時に、引き続き、終身医療保険特約の保障が必要な場合には、当該満了時に同特約の保険料を一括で支払う措置を講じるケースもあります。
もっとも、一括払保険料はかなりの金額(例.数百万円!)に上ることも少なくなく、例外的に、当該一括払保険料の分割払いを認める会社もありました。
7.直近データ
冒頭申し上げた、生命保険協会の統計データは、以下のURLからアクセス可能です。
https://www.seiho.or.jp/data/statistics/summary/xls/annual/bykt2025.3.xls
新契約および保有契約について、保険種類別のデータ(件数、保険金額)が把握できますので、是非、ご覧いただければと思います。
いかがでしたか。第三分野保険や(銀行窓販などによる)変額年金保険の台頭など、90年代の生命保険商品に比べて大きく様変わりした保険商品ですが、ESR(経済価値ベースのソルベンシー規制)の導入で、終身型保険がますます縮小している予感がする今日この頃です。
(ペンネーム:活用算方)