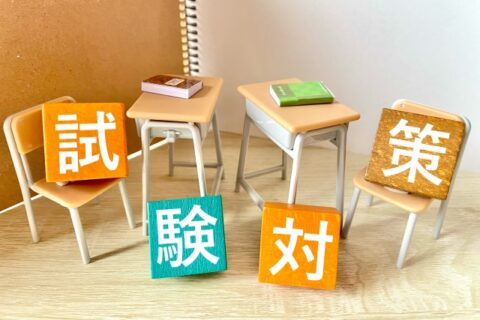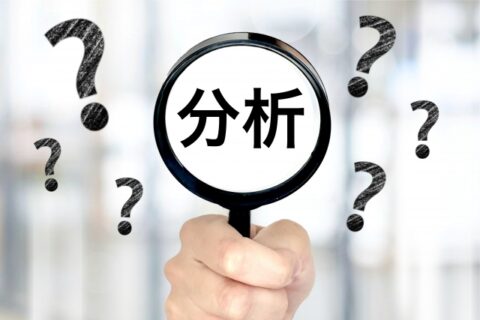先日、アクチュアリー試験対策の勉強会参加者から、“ゴーイング・コンサーンとは?”という(素朴な?)疑問を突き付けられて仕舞いました。
実際、アクチュアリー試験「保険2(生命保険)」の教科書『第6章 ソルベンシー』:
https://www.actuaries.jp/examin/textbook/pdf/hoken2-seiho_06.pdf
47ページに“ラン・オフとゴーイング・コンサーンの違い”が記載されていますが、質問者曰く、“保険会社にもかかわらず将来の新契約をカウントしないことに一体どんな意味・意義があるのか?”という疑義が根っこにあるようで、特に、実務経験の乏しい学生さんにとって至極ゴモットもな疑問という感じです。
そこで、今回のコラムでは、筆者のこれまで経験から、アクチュアリーにおける“ゴーイング・コンサーン”の観点も踏まえつつ、出来るだけ分かり易く、かつ、網羅的に思うところを述べてみます。
1.金融庁資料
ESR(経済価値ベースのソルベンシー規制)導入がいよいよ近づいて参りましたが、その一環で昨年10月末に金融庁から開示された資料『経済価値ベースのソルベンシー規制の概要(2024年10月31日)保険課保険モニタリング室』に“ゴーイング・コンサーン”という単語が登場します。
具体的には、当該資料4ページの「適格資本の分類に関する主な原則」で、銀行規制と同様に、今般、保険業界についても“Tier1、Tier2”といく区分が導入されるようでして、これらのうち、“ゴーイング・コンサーン”はTier1で登場します。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/hoken/20241031/00.pdf
2.日本公認会計士協会ホームページ
幸い、日本公認会計士協会ホームページで、“ゴーイング・コンサーン”が解説されているようで、具体的には、会社が将来にわたって継続していく前提を指すようですね。
その背景としては、企業の財務諸表は継続して事業活動を行うことを前提として作られていて、かつ、公認会計士として、ゴーイング・コンサーン情報の記載要否を判断する必要がある模様です。
なお、建物などの固定資産については、ゴーイング・コンサーンを前提とすれば“減価償却によって費用化”されますが、会社の倒産を前提とすると“処分価値で評価”されるという点は、まさに、決算業務としてのアクチュアリー実務にも通じる点があるように感じますね。
https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/post-10.html
3.日本アクチュアリー会教科書
上述の教科書47ページには、より厳密にいうと、ソルベンシー・マージン基準(=保険会社の債務)の捉え方について、ブレンダー博士は3つの考え方を列挙されています。
そのうち、ゴーイング・コンサーン以外の2つの概念について、
1)ワインドアップアプロ-チ:ある時期における債務をすべて清算
2)ラン・オフ・ベイシス:新契約の存在を仮定せず事業継続
という相違がありますので、“ゴーイング・コンサーンではない!”からといって、直ちに、会社をタタムとは限らない点にも注意が必要かもしれませんね。
4.保険会社の免許
ご案内のとおり、保険業の免許を付与する際、単年度黒字化の達成年度についてのシミュレーション結果の提出が求められます。
具体的には、生命保険会社が10年以内、損害保険会社が5年以内とされていますが、未達成でも“罰則規定”はありません!
ただし、純粋に新規(=白地=保有契約高ゼロ)での設立は認められていないようでして、実際、筆者が大変お世話になった某保険会社が保険業免許を申請した際、“既存の(クローズドの)保険会社を買収する前提にして欲しい”という趣旨のご要望を“やんわりと”主務官庁からご指導いただいてしまい、蓋を開けてみれば現状につながった苦い経験も記憶に新しいところではありますが。
5.社名変更と認知度
上述「4.」とも深く関係するのですが、筆者がこれまで大変お世話になった某保険会社が、(大人の事情により)数度にわたって“社名変更を繰り返した”ことから、ライバル会社と比較して認知度を大いに棄損してしまい、結果的には“親会社への吸収合併”という無残な結果を迎えることとなって仕舞いました。
まさに、ブランド力の維持・向上に関しては、決して会社名を変えないという強固な経営判断が必要であるという基本姿勢を、改めて深く考えさせられた事例となった格好ですね。
6.専門職としてのゴーイング・コンサーン
今更言うまでもないことではありますが、保険業法で保険計理人が規定され、その資格要件の1つとして「公益社団法人日本アクチュアリー会正会員」が位置付けられていることから、当然に、アクチュアリーは、弁護士、公認会計士、税理士、(歯科)医師および薬剤師などと並ぶ※「国家資格」の1つです。※認定資格ではありますものの、法律で保険計理人が規定されており、且つその保険計理人の要件にアクチュアリー正会員資格として求められており、正会員=国家資格という解釈に基づくものです。
筆者も正会員の端くれとして、これまで保険計理人やMOF担として金融機関でアクチュアリー業務に邁進して参りました。
その際、常に心の奥深くに秘めた思いとしては、
“たとえ、選手トレードなどで所属チーム(=保険会社など)が変わっても、
常にプロ選手として活動を続けたい”
という強い気概をもってアクチュアリー業務に邁進したいという点に尽きます。
いかがでしたか。私事で恐縮ですが、筆者は幸い、今年度から某大学(お台場方面)の非常勤講師(保険数学担当)を務めさせていただく機会にも恵まれ、週一回の講義のため、日夜、講義資料作成に鋭意勤しんでおります。
この「勤しむ」という言葉は国語学者である故・金田一晴彦先生が大好きな御言葉でして、この機会に使用できたことを大変有難く存じます。皆様におかれましても、『勤しむ』対象が御発見できますことを心より祈念いたしております!
(ペンネーム:活用算方)