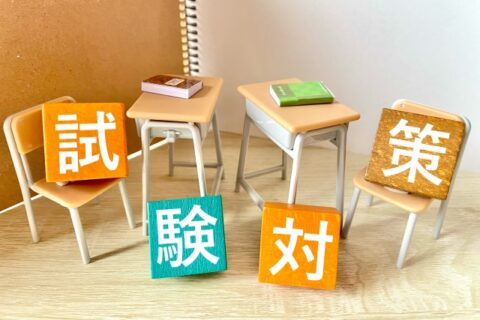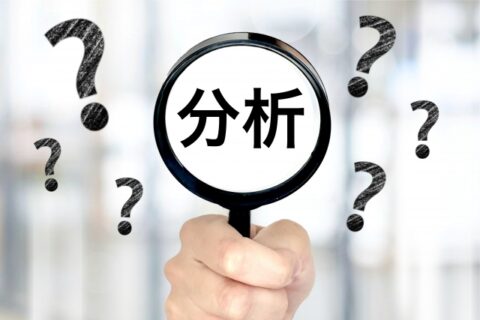先日、神保町の古書店巡りをした際、タイトルにある書籍を見つけました。
筆者も、実は、監査法人時代に「外部保険計理人」として、幾つかの少額短期保険業者(以下、「少短」という。)の経営に参画させていただいたのですが、その際、先方のご担当者が常に肌身離さず持参されていたのがこの書籍でした。
そこで、今回のコラムでは、改めて当該書籍をパラパラみながら、特に、アクチュアリーにとって興味深いテーマについて、順不同でご紹介することにいたします。
なお、書籍刊行は、平成18年(2006年)10月30日(第1刷)ですので、現在の法令等と異なる内容があり得ることを、何卒ご容赦ください。
1.準会員で保険計理人になれる!?
平成8年(1996年)の保険業法改正時、いわゆる救済措置(経過措置)として、日本アクチュアリー会準会員でも、保険会社の保険計理人に就任できることが規定されていました。
その後、法令等の改正により、現在では、少なくとも、保険会社の保険計理人に就任するためには、日本アクチュアリー会正会員であることが要求されています。
一方、少短においては、それまでの無認可共済という建付けを勘案し、たとえ準会員でも、保険計理人に就任できることが規定されています。
“社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に5年以上従事した者(146ページ)”
なお、当該ページの欄外注記にいれば、この要件を満たさない者を保険計理人に選任した場合、当該少短の取締役等に100万円以下の過料に処されることがあるようですので、かなり厳しいルールになっているようにも思われます。
2.保険計理人の権限
少短の保険計理人が行う業務は、保険会社の保険計理人より広範囲であり、具体的には、
“登録申請時および商品改定時における保険料および(注.保険業法第4条(免許申請手続)では「及び」と記載)責任準備金の算出方法書の確認業務(143ページ)”
が含まれます。
保険会社の場合、当該確認業務は主務官庁である金融庁が行いますが、少短の主務官庁は、通常、各財務局が担当されるため、監督側の人員不足などに配慮した規定と考えられます。
いずれにせよ、保険会社における保険計理人経験者が少短の保険計理人業務を行う場合に、この点にも留意する必要がありますね。
3.責任準備金
少短の責任準備金は、
① 普通責任準備金
② 異常危険準備金
③ 契約者配当準備金等
から構成されます。(139~140ページ)
したがって、法令上の少短の枠組みは、(生命保険会社ではなく)損害保険会社の枠組みが適用されています。
なお、①の普通責任準備金については、“未経過保険料と初年度収支残高のいずれか大きい金額を積み立てる”こととされている点にも留意が必要です。(139ページ)
4.損保は2年、生保は1年
少短は、生命保険・医療保険および損害保険の引き受けが同時に行えますが、これらの保険期間の上限は一律ではありません。
具体的には、生命保険・医療保険が1年で、損害保険が2年とされています。
なお、損害保険の2年については、以下の注釈があり、また、契約の更新については、完全なる自動更新は認められていない模様です。
“契約期間が通常2年である賃貸借契約等に関連して締結されることが多いという既存のいわゆる根拠法のない共済の実態等を踏まえたもの(64ページ)”
5.外部監査を受ける基準
資本金または基金の総額が3億円以上となる場合には、外部監査を受ける必要があります。逆に言えば、当該総額が3億円未満であれば、当該監査を受ける必要はありません。
なお、株式会社では、会社法第2条第6項における『大会社(=資本金5億円以上または負債200億円以上)』に該当すれば、会計監査を受ける必要があります。
6.番外編
最後は、本件書籍の記載事項ではありませんが、今年度末から導入される「ESR(経済価値ベースのソルベンシー規制)」において、少短は対象外です。詳しくは、金融庁ホームページ(https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250723/20250723.html)にある、
『(別紙17)経済価値ベースのソルベンシー規制に関するQ&A』4ページ⑥:
“連結ソルベンシー・マージン比率における少額短期保険業者の取扱い
例えば次の取扱いとすることが考えられる。
a. 経済価値ベースのバランスシートにおいては、保険負債等の経済価値評価の額への評価替えを行わない。
b. 所要資本は、保険事業の所要資本の計算の対象とはせず、少額短期保険業者単体のソルベンシー・マージン比率に用いるリスク相当額(平成18年金融庁告示第14号第4条に基づき算出される額)を、非保険事業の所要資本に加える。”
をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/hoken/20250723/17.pdf
いかがでしたか。日本少額短期保険協会によれば、直近の決算において、「保有契約件数 1,248万件(前年度比108%)」、「収入保険料1,536億円(前年度比107%)」という状況でして、依然として成長しつづけています。
https://www.shougakutanki.jp/general/info/2025/news20250704.pdf
生命保険・損害保険に次ぐ『第3の保険勢力』として、ますますその存在意義が注目されるところです。
(ペンネーム:活用算方)