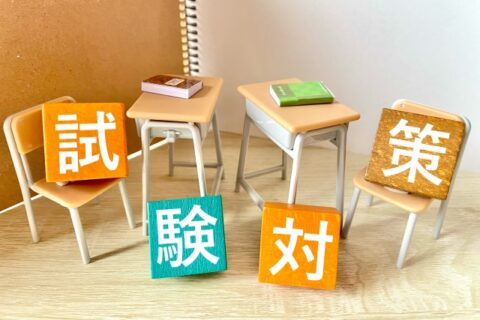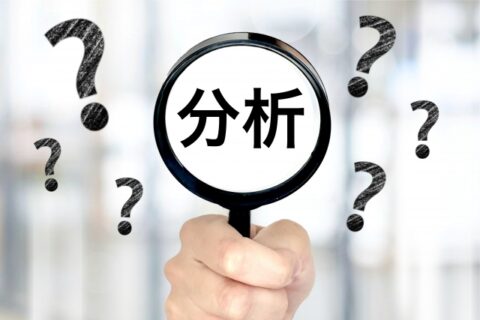2025年のアクチュアリー試験まであと数か月となり、受験生の皆様におかれましては、そろそろラストスパートに突入される時期かと存じます。
また、2022年度からスタートしたCBTも定着しつつありますので、特に、初受験の方は是非、体験版(http://it.prometric-jp.com/tutorial/actuaries/first_stage_exam/index.html)で、操作方法などをチェックされると良いでしょう。
そこで、今回のコラムでは、アクチュアリー試験のうち「第1次試験(生保数理)」について、重要性が高いと考えられる論点を幾つかご紹介いたしましょう。
なお、当コラムに関連する過去のコラム(https://www.vrp-p.jp/acpedia/4690/、https://www.vrp-p.jp/acpedia/4249/、https://www.vrp-p.jp/acpedia/3677/、https://www.vrp-p.jp/acpedia/3162/、https://www.vrp-p.jp/acpedia/2366/)も併せてご覧いただけますと幸いです。
1.昨年の合格率
以前のコラム(https://www.vrp-p.jp/acpedia/5482/)でご紹介いたしました通り、2024年度の生保数理の合格率は46.2%(https://www.actuaries.jp/info/pdf/20250328.pdf)という極めて高水準でしたので、今年は難化が大いに予想されるところです。
したがって、今年の対策としては、昨年同様、過去問のうち、
1) 合格率が低かった年の過去問を重点的に学習すること
2) 特に、難問と呼ばれる過去問を重点的に学習すること
3) 用語の定義(例.観察死亡率など)を正確に覚えること
といった試験対策が合格への秘訣となるかもしれませんね。
2.合格率の推移、難問例
上記1.1)については、上記のリンク(https://www.vrp-p.jp/acpedia/5482/)で過去の合格率推移がお分かりいただけますので、特に、合格率が低かった年度(例.平成16年度など)の過去問を重点的に学習されるとよいでしょう。
また、上記1.2)については、例えば、上記のリンク(https://www.vrp-p.jp/acpedia/4690/)をご覧ください。(←もちろん、当該コラムで紹介した難問以外にも難問は存在します。)
3.Thieleの微分方程式
2020年度問題2(3)で、保険料払込方法が(一時払ではなく)平準払(=連続払全期払込)という条件で、Thieleの微分方程式に関する出題が初めてなされました。
初出ということもあり、Thieleの微分方程式を解くためのヒントが掲載されましたが、今後は当該ヒントがない形での出題が十分考えられますので、しっかりと復習された方がよいように思います。
4.副集団から主集団への異動
こちらも初出題ですが、平成29年度問題2(1)で、多重脱退表(例.死亡・就業不能脱退残存表など)における、“副集団から主集団への異動”を考えた問題が出されました。
特に、教科書(下巻)『第13章 就業不能(または要介護)に対する諸給付』では、当該異動は(モデルの複雑さから)考えないというスタンスですので、当該異動を加味した出題は、資格試験要領違反(=第1次試験(基礎科目)の出題は教科書に限定)であるかのような『誤解』を導く可能性も否定できませんが、筆者のみる限り、決して違反していないように思います。
興味のある方は、今一度、教科書(上巻)『第3章 多重脱退表』を再読ください。
5.5種類の死亡率
「単生命表における死亡率」、「中央死亡率」、「多重脱退表における(絶対ではない)死亡率」、「多重脱退表における絶対死亡率」、「観察死亡率」の定義がすぐに浮かんでくるレベルであれば、十分に合格レベルと言えるかもしれませんね。
いかがでしたか。昨年のコラムでも触れましたが、アクチュアリー試験は直前になればなるほど、緊張感のために、なかなか集中できない日々が続く可能性もあります。今回ご紹介した内容をしっかりと押さえた上で、良い結果につながることを祈念しております。
(ペンネーム:活用算方)