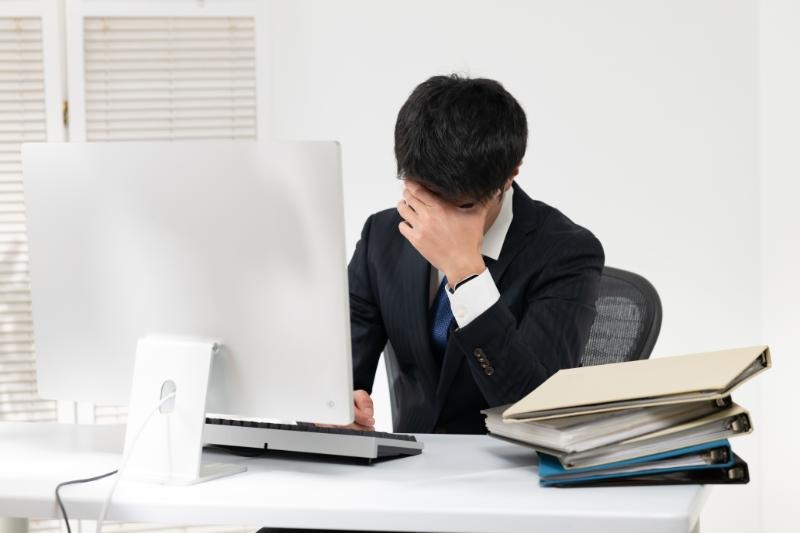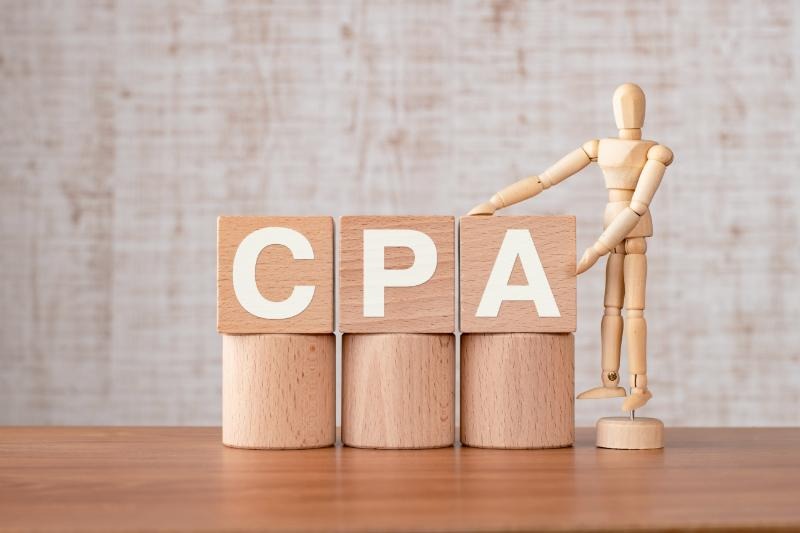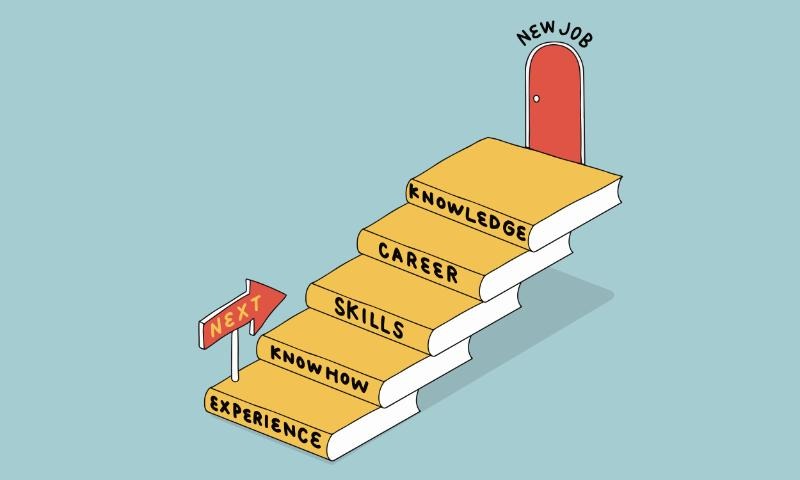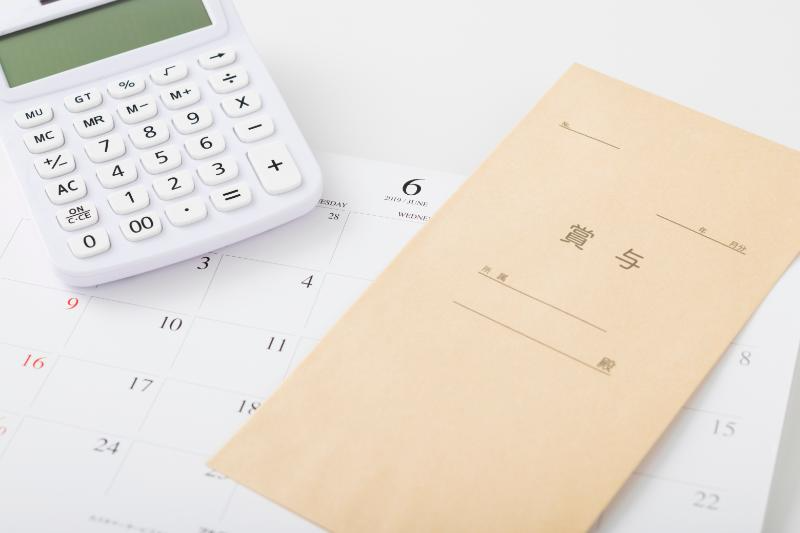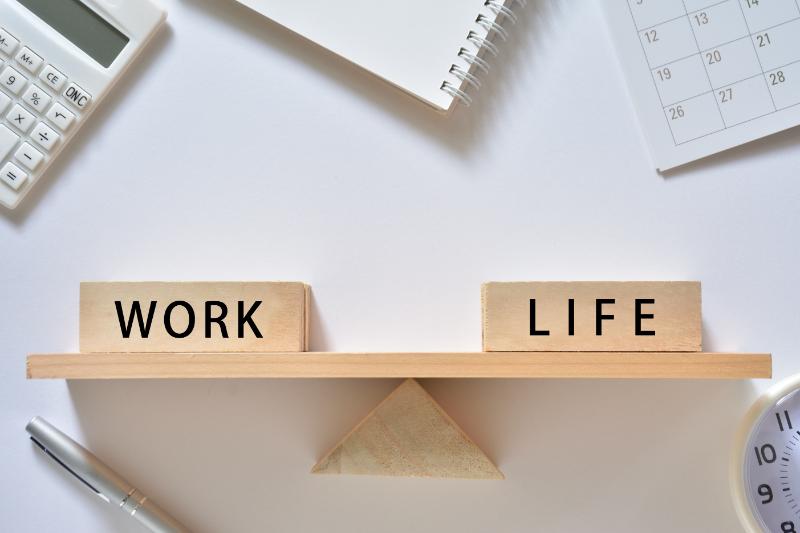公認会計士と経理の違い【基本編】
「公認会計士と経理って、どちらも会計の仕事では?」と感じる方も多いかもしれません。たしかにいずれも会計に関わる点では共通していますが、公認会計士は国家資格を有する専門職であり、経理は企業内での業務を指します。そのため、業務範囲や役割、キャリアパスなどには明確な違いがあります。まずは、両者の根本的な違いを基本的な視点から整理してみましょう。
公認会計士は国家資格が必要、経理は資格不要でも可
公認会計士は、国家試験に合格し、一定の実務経験を経て登録を受けた“国家資格保持者”です。主に監査業務を担う専門職であり、その資格を有することで「公認会計士」という名称を使用することが認められます。一方、経理職には特定の資格は必須ではなく、簿記や会計知識を持っていれば未経験でも就業可能な場合が多く見られます。
もちろん、会計士資格を持っていることは経理としても大きな強みになりますが、制度上は無資格でも従事できる職種である点が、公認会計士との大きな違いです。
会計士は監査・コンサル業務、経理は自社の会計処理
公認会計士の主な業務は、第三者的な立場から企業の財務諸表の正確性をチェックする「監査」にあります。加えて、近年はアドバイザリーやコンサルティング業務に従事するケースも増えており、企業外部の立場から信頼性や改善提案を行う役割を担っています。
一方で、経理職は企業の内部に所属し、自社の取引や決算、税務申告など日々の会計・税務業務を直接的に処理していく実務担当です。つまり、公認会計士が「外から見る立場」であるのに対し、経理は「中から支える立場」と言えるでしょう。
公認会計士と経理の仕事内容の違い
同じ「会計」に関わる職種であっても、公認会計士と経理ではその業務の範囲や視点が大きく異なります。ここでは、それぞれの代表的な仕事内容を確認しながら、役割の違いを明確にしていきましょう。
公認会計士の主な業務
公認会計士の中心的な業務は「監査」です。企業が作成した財務諸表に対して、その正確性や信頼性を第三者の立場から検証し、適正な報告書を発行します。特に上場企業にとっては、外部監査は法的に義務づけられており、会計士の果たす役割は極めて重要です。
また近年では、FAS(Financial Advisory Services)をはじめとするアドバイザリー業務に従事するケースも増えており、M&Aにおける財務デューデリジェンスやバリュエーション、事業再生支援、不正調査など、経営課題に対して多角的な支援を行う場面も多くなっています。
経理の主な業務
経理は、自社内で発生する日々の取引を正確に記録し、最終的には決算書の作成や税務申告へとつなげていく実務を担います。具体的には、売上・仕入の記帳、請求書の発行、経費精算、仕訳入力、月次・四半期・年次決算対応など、企業の「お金の流れ」を記録・管理する業務が中心です。
また、企業によっては、財務や税務、内部統制、開示書類の作成まで幅広い業務を担うこともあります。業種や企業規模によって求められる範囲は異なりますが、経理はまさに“企業活動の根幹を支える存在”として重要な役割を果たしています。
公認会計士が経理に転職するメリットとは?

監査法人での業務にやりがいを感じながらも、将来的なキャリアや働き方を見直したいと考える公認会計士は少なくありません。そうした中で、事業会社の経理職へ転職することは、多くの面で新たな可能性を広げる選択肢となり得ます。ここでは、会計士が経理に転職することで得られる主なメリットを4つご紹介します。
クライアントワークから自社貢献型の業務へ
監査業務は第三者として企業の財務諸表をチェックする立場であり、あくまで“外からの支援”にとどまります。一方、経理職は企業の内部に入り、実際の業務や意思決定のプロセスに直接関わることができます。「自分の働きが会社の成長に直結している」と実感できるのは、事業会社で働く大きな魅力のひとつです。クライアントワーク特有の距離感に物足りなさを感じていた方にとって、自社貢献型の業務はやりがいを強く感じられるでしょう。
ワークライフバランスが整いやすい
監査法人では、繁忙期やタイトな納期対応により、長時間労働や休日出勤が続くことも珍しくありません。対して、事業会社の経理職は、スケジュールがある程度安定しており、ワークライフバランスを保ちやすい環境であることが多いです。特に上場企業では決算期などの繁忙期はあるものの、それ以外の時期は比較的落ち着いて働けるケースも多く、ライフステージに合わせた働き方を選びたい方に適しています。
業務に対する意思決定の裁量が大きい
経理職は単に数字を処理するだけでなく、経営判断の材料となるレポートを作成したり、予算や資金繰りの管理などにも関与します。ポジションによってはCFOや経営層に直接提案を行う機会もあり、現場レベルでの意思決定に関与できる点が特徴です。監査法人のように“報告の受け手”で終わるのではなく、自らの知見をもとに“主体的に会社を動かす”側に回れることは、大きなやりがいにつながります。
経理からCFOや経営企画へのキャリアも可能
経理は、企業の財務情報を扱う最前線であり、経営の全体像に触れる機会が多いポジションです。そのため、実務経験を積むことで、将来的にCFO(最高財務責任者)や経営企画、IR、財務戦略といった経営中枢へのキャリアアップも十分に視野に入ります。特に公認会計士としての専門性を活かせば、上場準備企業や急成長スタートアップなどで幹部候補として迎えられることも珍しくありません。
会計士が経理職を目指す際の就業先の選び方
経理職といっても、企業の規模や業種、フェーズによって仕事内容や求められるスキルは大きく異なります。会計士としての専門性をどう活かしたいのか、どのような働き方をしたいのかによって、選ぶべき就業先も変わってきます。ここでは、代表的な3つの選択肢を紹介します。
上場企業:内部統制や開示業務に携われる
上場企業の経理部門では、制度会計を中心に、開示書類の作成、IFRS対応、内部統制の整備・運用など、高度で専門的な業務に関与できます。特に会計士として監査の経験がある方にとっては、これまでの知識がダイレクトに活かせる環境であり、スムーズなキャリアチェンジが可能です。また、組織が整備されていることが多く、安定した働き方を望む方にも適しています。
ベンチャー企業:幅広い会計領域に関与できる
ベンチャー企業では、少人数の体制で経理業務を回していることが多く、日常の仕訳入力から資金調達、経営陣へのレポーティングまで幅広い業務に関わることができます。決まったルールが少ない分、柔軟性や主体性が求められる反面、スピード感のある成長環境で経験を積めるのが魅力です。上場準備段階の企業ではIPO対応に関わることもあり、会計士としての専門性が強く求められます。
外資系企業:英語力を活かせるチャンスも
英語スキルを活かしたい会計士にとって、外資系企業の経理職も有力な選択肢です。本国へのレポーティングや海外チームとの連携が発生するため、読み書き・会話を含めたビジネス英語が必要になるケースが多いですが、その分、グローバルな視点や先進的な経理体制を学べる環境があります。また、企業によってはUSCPAやIFRSの知識を持つ人材が重宝されることもあり、スキルと志向がマッチすればキャリアアップの場として非常に魅力的です。
会計士から経理へ転職する際の注意点

会計士としての専門知識や監査経験は、経理職においても大きな武器になりますが、社内業務の現場に飛び込む以上、いくつかの注意点も存在します。スムーズに定着し、長期的なキャリアを築いていくためには、以下のような視点が欠かせません。
監査目線からの脱却と実務への慣れ
監査法人では、企業の財務諸表を外部からチェックする“評論家”の立場で業務を行っていた会計士も、経理職では“実務の担い手”に変わります。監査時代と同じ感覚で理想を追い求めすぎると、現場とのギャップに戸惑う可能性があります。実際の業務では、期限やシステム上の制約、リソースの問題など、理想通りにいかないケースも多いため、柔軟な姿勢と現場感覚を養うことが重要です。
求められる役割の違いを理解する
監査では「正確性」や「客観性」が重視されるのに対し、経理職では「効率性」や「実行力」がより求められます。また、業務プロセスの改善や部門間の連携など、組織の中で“どう動くか”が成果につながる場面も増えます。過去のスキルや立場に固執せず、会社の中で求められる役割を柔軟に受け入れることが、経理職での成長を後押しします。
組織内での調整力・協調性も求められる
事業会社の経理は、営業部門や人事、経営企画など多くの部署と連携しながら業務を進めていきます。そのため、社内での調整力や円滑なコミュニケーション力も不可欠です。監査法人のように専門家同士で完結する環境とは異なり、会計に詳しくない相手と折衝する機会も多くなるため、わかりやすく説明する力や柔らかい物腰も評価されるポイントとなります。
経理実務未経験者歓迎の求人かどうかを確認
経理職への転職を検討する際は、「経理実務経験不問」または「会計士歓迎」と明記されている求人を選ぶことが成功の鍵になります。特に上場準備中の企業やベンチャー企業では、会計士の知識や監査経験を高く評価してくれる傾向があります。自身のスキルセットと求人要件のマッチ度を確認したうえで、転職活動を進めることが重要です。
公認会計士が経理職に転職した成功事例
ここでは、公認会計士として監査法人で活躍されていた方が、経理職へ転職し、新たなキャリアを築いた実例をご紹介します。
30代・男性のケースでは、大手監査法人で会計士として幅広い業種を担当し、会計監査に加えてIFRS関連のアドバイザリー業務や海外向けの案件も含め、シニアマネージャーとして豊富な経験を積んでこられました。しかし、今後のキャリアを棚卸しする中で、「より事業に寄り添った形で専門性を発揮したい」という思いが強くなり、大手フィンテック企業の経理部門(連結担当)への転職を決意されました。
この転職によって、年収は1250万円から1300万円へとアップ。連結会計部門での各種プロジェクトを牽引することが期待されており、ベンチャー企業特有のスピード感やダイナミズムのある事業展開の中で、自身の専門性を活かしながら積極的に取り組まれています。
「監査する側」から「経営の一翼を担う側」へと視点を変えることで、キャリアに新たな意義とやりがいを見出した好事例と言えるでしょう。
VRPパートナーズは公認会計士の転職をサポートします

監査法人での業務にやりがいを感じながらも、「このままでいいのだろうか」「もっと事業に近い場所で働きたい」と感じ始めたとき、自分一人でキャリアの選択肢を広げるのは簡単ではありません。VRPパートナーズは、そんな悩みを抱える公認会計士や試験合格者の方々を専門にサポートする転職エージェントです。
私たちは、FAS(Financial Advisory Services)やアドバイザリーファームをはじめ、公認会計士が専門性を発揮できる多様なフィールドに精通しています。FAS領域における財務デューデリジェンスやバリュエーション、M&A支援をはじめ、ガバナンス強化や業務改善コンサルなど、ご志向に合わせたキャリアパスをご提案いたします。
また、上場企業やスタートアップ企業、ファンドの投資先などの事業会社における経理・財務・経営企画などのポジションでの採用実績もございます。。「これまでの経験をどう活かせるのか」「今の自分に合う環境はどこか」といったお悩みも、ぜひご相談ください。
キャリアの方向性に迷いがある方も、まずは一度、ご相談ください。未来の選択肢がきっと広がるはずです。
まとめ
公認会計士と経理職は、同じ会計領域に属していながらも、求められる役割や働き方に大きな違いがあります。監査法人では外部の視点から企業を見る立場である一方、経理職は企業の内部から実務を担い、経営に近い立場で貢献する役割です。
監査経験を活かして経理職へ転職することで、「自社に貢献している実感がほしい」「ワークライフバランスを整えたい」「経営判断に関与できる裁量ある仕事がしたい」といった希望を叶えることが可能です。また、経理からCFOや経営企画といった経営中枢へのキャリアパスも拓かれており、将来の選択肢も広がります。
一方で、監査目線からの脱却や組織内での協調性といった新たな視点も求められるため、自分に合った企業や職場環境を見極めることが成功の鍵になります。
VRPパートナーズでは、公認会計士としてのご経験を最大限に活かしたキャリア支援を行っています。転職活動を始める前の情報収集の段階からでも、お気軽にご相談ください。あなたにとって最適なキャリアの道筋を、一緒に描いていきましょう。